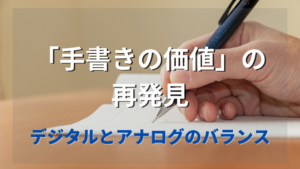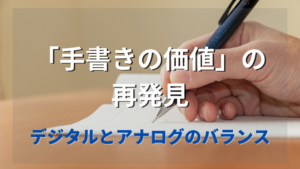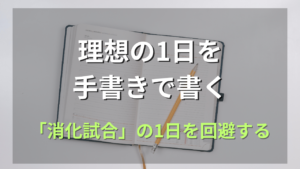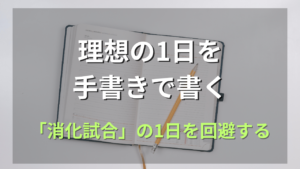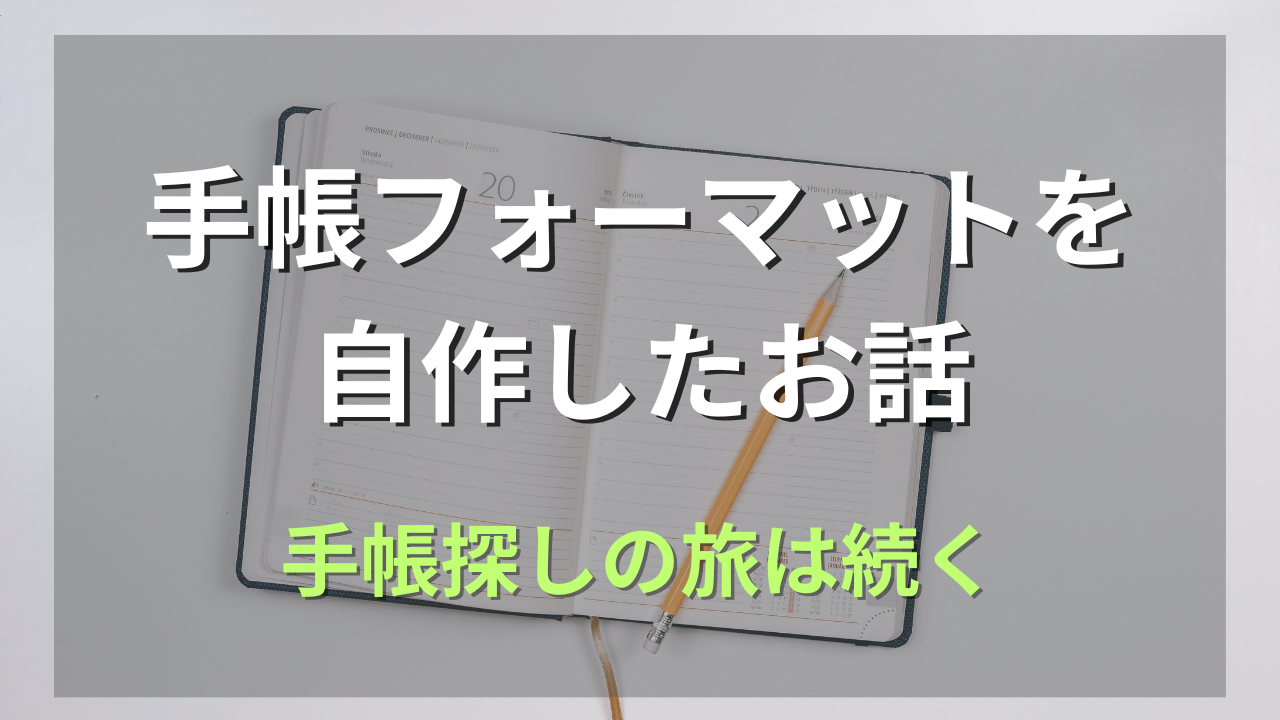これまでの人生、手帳探しには相当な時間を費やして来ました。
毎年12月になると東急ハンズや書店を複数巡り、大抵1日では即決できず、2週間ほどかけて「理想の手帳」を追い求め、最後は「これしかない!」と意を決して購入します。
その後、2週間ほどで何かしらの細かい点が気になり始めてすぐに買い替えたり、または4月始まりの手帳が書店に並ぶと浮気性が再発します。(このパターン、英語学習と同じですね (^ ^;))
ここ3年ほどは「行動科学のビジネス手帳」という素晴らしい手帳に出会ったおかげで状況は改善されていましたが、最近になって「1日1ページ型」の手帳で毎日をしっかり振り返りながら過ごしたいと思い、以下の手帳を購入しました。
この手帳も良い感じなのですが、使いながら「もっと振り返りのスペースが欲しい」と思う時があります。
ただ、書店や各手帳メーカーのHPを探しても、このA5サイズよりも大きいデイリータイプの手帳は見つかりませんでした。
 管理人の願い
管理人の願い1日1ページ、A4サイズ(できれば横型)で、0〜24時までバーティカル型のスケジュールを書き込めて、右側にたっぷり余白のある手帳は世の中に存在しないものか・・・
ここまで考えた後、以下の思考に至りました。



……無いなら自分で作ればいいじゃないか!
なぜもっと早く気づかなかったのか。
自分で作れば、求める条件をすべて盛り込むことができるはずです。私の中で衝撃が走りました。
自作したフォーマット
という経緯を経て、私の作ったフォーマットがこちらです。


以下にこだわりポイントを挙げていきます。
こだわり① スケジュール部分は0〜24時・バーティカル型
世の中の手帳は、7〜21時頃までしかカバーされていないものが多いです。
私の普段の就寝時間は24時なので、これでは21〜24時の過ごし方が曖昧になってしまうという問題がありました。
加えて、「1日は24時間あること」を明確に意識しながら過ごすためにも、0〜24時まですべて書かれた手帳が欲しいと思っていました。(市場に商品がない=少数派のニーズであることは承知しています)
また、テキストは横書きで書いていくため、ホライズン型の手帳ではすぐに狭苦しくなってしまいます。
以下の本で提唱されているとおり、手帳はバーティカル型一択です。
こだわり② スケジュールは2列分あり
大きな特徴は、スケジュールを書き込む列が「2つ」あることです。
この2列目は、例えば以下のような使い方ができます。
- 【例1:理想と現実の1日の比較】
- 左側:事前に立てたスケジュール(通常の予定)(青字)
- 右側:実際の1日の行動がどうだったか(黒字)



これによって、「理想と現実のギャップ」を認識し、PDCAを回しやすくなります。私のメインの使い方はこれです。
- 【例2:各予定の「目的」を書き込む】
- 左側:事前に立てたスケジュール(通常の予定)
- 右側:各予定の目的を書く
- (平日の例)14:00〜14:30 キックオフ会議の目的
- ◯◯のプロジェクトの意義をメンバーに理解してもらい、協力体制を作る
- (休日の例)家族でふれあい動物園へ行く目的
- 娘に動物を愛でる優しい心を養ってもらう
- ささやかだが幸せな家族の思い出を積み重ねる
- (平日の例)14:00〜14:30 キックオフ会議の目的



これは、「先延ばしと挫折をなくす計画術」という本のプロローグに書かれていた技術です。
やってみると分かりますが、目的(=何を達成するための時間か)を書くことで、それに向けて準備すべきことが分かるほか、その時間中の意識も明確に変わります。ちなみに私の場合、1日の終わりに実績(その時間から得られた成果・学び)を書くこともあります。
- 【例3:自分と家族の予定】
- 左側:自分のスケジュール
- 右側:家族の予定



この使い方は、特に休日に有効です。休日は「予定が自分一人では完結しない」という点で予定作成の難易度が上がるため、このフォーマットで可視化します。私の場合、「妻と娘が友人宅へ行っているこの時間帯にブログを書き上げよう」といった具合で計画を立てています。
こだわり③ フリー記述スペースはたっぷり(方眼紙で)
左側のスケジュール欄と同じくらい大事なのが、右側のフリースペースです。
シンプルな方眼紙ですが、1マスの幅、破線の種類、太さにこだわりました(笑)
シンプルだからこそ、使い方が無限にあることが最大のメリットです。
世の中では多種多様な「振り返りの方法」が提唱されていて、それぞれに良い点・悪い点があると感じています。
正確には、「その日の状況によって、適した振り返りの方法は異なる」ということです。
この気づきを与えてくれたのは、古川武士さんの「こころが片づく書く習慣」という本でした。
上記の本では、実に18通りの「振り返りのフレームワーク」が紹介されています。
著者の古川さんの「すべてを使う必要はなく、あなたの状況に応じて必要なものをピックアップして活用してください」という言葉を読んだ時、「手帳を使った日々の振り返りにおいても、フレームワークを柔軟に変えられることがベストではないか」という考えに至りました。
さらに、これだけスペースがあれば、複数の観点で振り返ることも可能です。例えば、上半分はGPS(下記参照)、左下はネガティブな気持ちを紫字で、右下には感謝日記を緑字で書く、といった使い方ができます。
適当なフレームワークを選んだ上で、「余白がある」ことでそれを埋めようと脳が考え始めます。
この「フレームワーク✖️十分な余白」こそが、日々の振り返りの極意だと考えています。



最近私が主に使っているフレームワークは「GPS」です。
“Good”(良かったこと)、 “Problem”(できなかったこと)、”Solution”(次にどうするか)というシンプルなものですが、書いていると思考が整理されていくのを感じます。
また、定期的に過去の”Solution”のストックを読み返すことで、今の自分が「過去の自分の反省を活かせているか」が浮き彫りになります(^ ^;)
唯一のデメリット:自分で印刷する必要がある
良いことだらけの自作手帳フォーマットですが、唯一のデメリットは自分で印刷して綴じる必要があるという点です。
我が家にはプリンタがないので、コンビニのマルチコピー機で印刷します。1枚10円 → 365枚印刷すると3,650円。立派な高級手帳と言ってよい値段です。
また、印刷後は穴を開けて2リングファイルに綴じるのですが、やはりページをめくりにくいと感じます。この点は、製本された市販の手帳に軍配が上がります。
ただ、世間にはリフィル手帳というものも広く普及しているので、これも慣れなのかもしれません。
まとめ
今回は、手帳探しの沼にハマりすぎた結果として、自作手帳フォーマットに挑戦したお話を書きました。
先日購入した高級手帳(5,390円!)をまったく使わなくなるのもあまりに惜しいので、こちらも時々使いつつ、最適なスタイルを模索します。
私の手帳探しの旅はもう少し続きそうです。
(編集後記)誤変換で思考が寸断されたお話
記事中盤の「かきあげよう」という文字を変換した時、「かき揚げ用」が最初に表示されて目を疑いました。本当に、Macの日本語入力はどういう基準で変換候補が表示されているのか謎です・・・